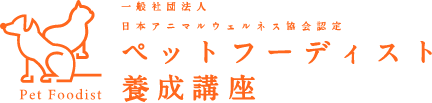修了生の声

「療法食を食べない場合のご相談対応」をレベルアップできました
永井さん【16期生】
現在のお仕事
動物病院に勤務して9年目です。
仕事は多岐にわたります。診療補助、お薬処方時の説明、入院管理、手術時の麻酔管理、入院中の動物の食事対応、電話対応などなど。愛玩動物看護師が国家資格となって以降、採血や投薬は動物看護師も対応が可能になり、勉強会でスキルを高めていっているところです。当院は獣医師が多いため、そこまで実施の機会は多くはないですが、補助や準備は勉強会を経て徐々に対応がスムーズになってきているところです。
ペットフーディスト資格取得後の変化
実はホリスティックケア・カウンセラーの資格を先に取得して、診察後の家庭でのケアアドバイス力はアップしたのですが、栄養学は苦手だったんです。
例えば、ペットフードの成分の見方や、カロリーと給与量の計算の仕方などの知識があいまいだったのですが、ペットフーディストの受講で改めてそこを復習できたことと、ペットフードごとの栄養成分がどう異なっているかを把握し、複数の商品を比較する知識がついたことが良かった点です。
また、「具体的な食材のアドバイス」もできるようになりました。飼い主さんって市販のフードやおやつだけでなく「食材なら何を与えるといいか」を質問する方が多いんです。ペットフーディストのテキストの食材の成分表から「タンパク質が多いのはこの食材」など、以前はあまり意識していなかった食材ベースの知識を増やせたことで対応できるようになりました。
さらには、「病気の動物の食事の理解」が深まったことで提案の幅が広がりました。
病院としては、診察後に療法食を処方するのが一番スムーズではありますが、後日「おいしくないので食べてくれない」というご相談がくるのは日常茶飯事。ですので、トッピングやおやつでどう対応するか…というご提案が必要になります。ペットフーディスト取得後は、「栄養学」「食材」「病気の食事管理」の知識を使って「低脂肪がよいのでチーズよりささみがいいですよ」などお伝えする内容をバージョンアップさせることができました。
手作り食やトッピングをしている方は、「これまでは〇〇を△△グラム与えてきたけど、これは継続していいですか」などさらに細かい質問をされてくるため、計算しながらお答えしています。
ただ、食材でアレンジを加える前に、まず療法食や通常のフードの各商品の理解とお客様への説明が必須なため、そちらの知識も同時進行でつけていく必要があります。1つの療法食を食べなかったら、成分値が近いほかの商品にチェンジしていただくことが次の選択肢になりますからね。メーカーが異なると表示の仕方も異なるため、メーカーさんのセミナーや独学などでまだまだ勉強の日々です!

今後の目標
まだ栄養学が苦手なので、知識を定着させたり深めたりして、その子に適したごはんを自信をもって提案できるようになりたいです。
また、ペット業界にはホテルやシッターなど動物看護師がいると心強く感じていただけるサービスや、動物看護師ならではの活躍ができる現場がたくさんあると思います。今すぐではないですが、個人的にはシェルター職員にも興味があり、いつかそういった業種でお役に立てることがあれば…と考えています。